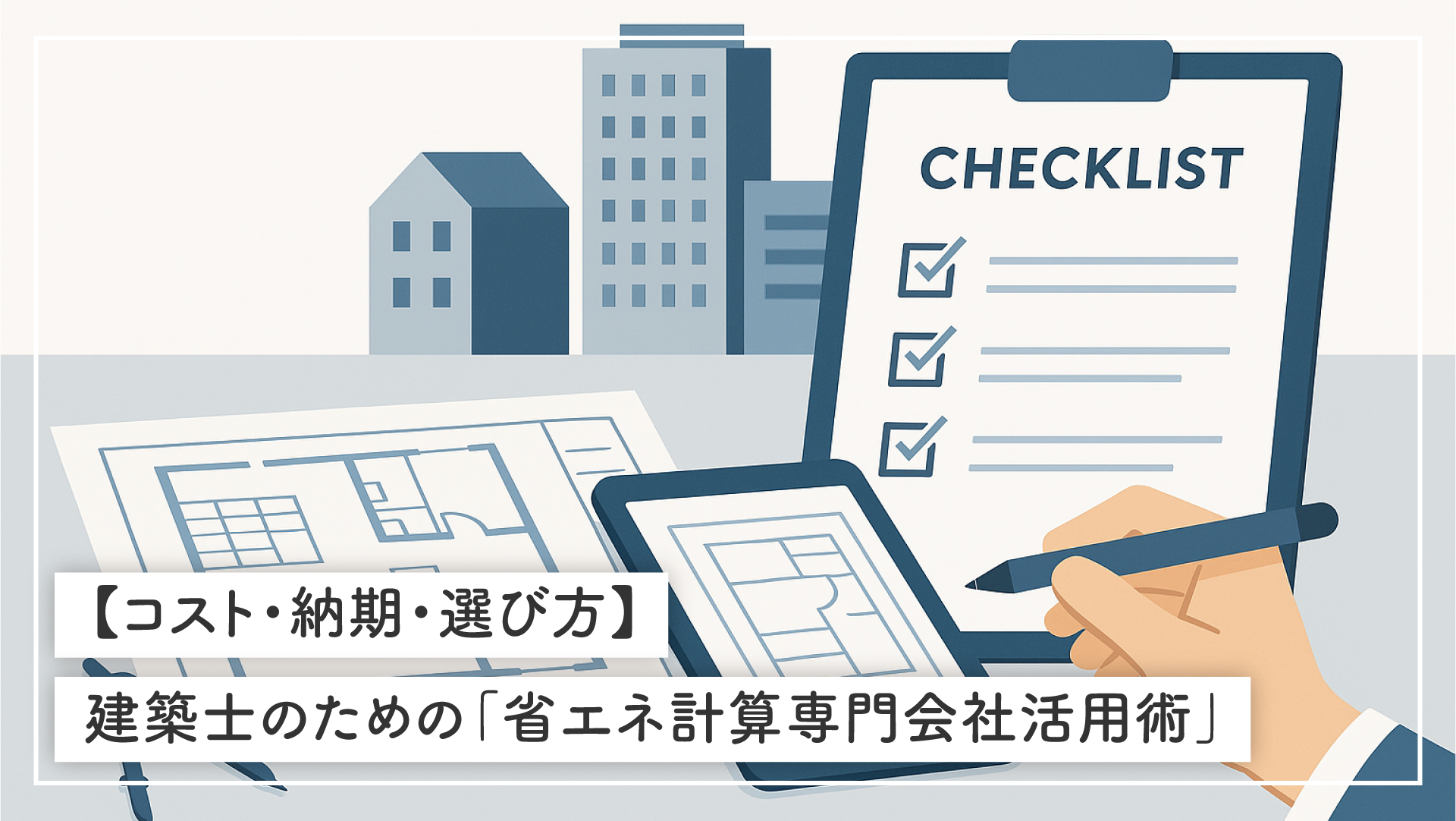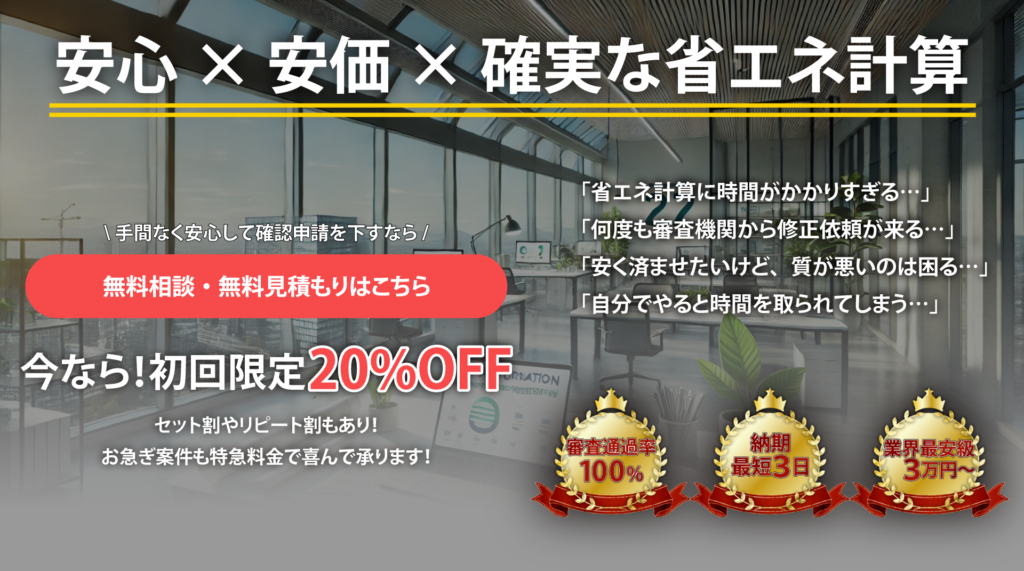「省エネ計算の作業に時間がかかりすぎて、本業の設計に集中できない…」
「複雑な法改正にも対応しなければならず、何から手をつけていいかわからない…」
こうした悩みを抱える建築士の方は少なくありません。
特に近年は、省エネ適判やBELS、住宅性能評価など建築物省エネ法に関する対応がますます煩雑になっており、設計実務と並行してこれらの計算業務をこなすのは大きな負担となっています。
そこで今、多くの設計事務所や工務店が活用しているのが、「省エネ計算専門会社」へのアウトソーシングです。
省エネ計算のプロに依頼することで、作業時間の削減だけでなく、申請精度の向上やスムーズな審査通過にもつながるなど、数多くのメリットがあります。
本記事では、建築士の方向けに
- 省エネ計算を外注するメリット
- 実際にかかるコストや納期
- 専門会社を選ぶ際のチェックポイント
などをわかりやすく解説します。
「時間を有効活用したい」「確実に申請を通したい」と考えている建築士の方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 省エネ計算を外注(アウトソーシング)するメリットとデメリット
- 実際にかかる費用の目安と納期の例
- 依頼先の専門会社を選ぶ際のチェックポイント
- 計算を依頼する際に用意しておくべき図面や情報
- 信頼できるパートナーを見つけるための考え方
建築士が省エネ計算を外注する時代
建築物省エネ法の改正や審査の厳格化により、設計者が自ら省エネ計算を行うハードルは年々上がっています。
以前は設計図面さえしっかりしていれば通っていた確認申請も、いまでは詳細なエネルギー計算や根拠資料の添付が必須となり、専門的な知識や経験が求められるようになっています。
忙しい設計業務との両立が困難に
設計業務と並行して省エネ計算まで対応するのは、特に個人事務所や小規模な設計事務所にとって大きな負担です。
その結果、
- 納期がタイトで間に合わない
- 審査で不備を指摘されて再提出になる
- 最新の法改正に追いつけない
といった課題を抱える設計士が増えています。
審査機関も「専門会社の活用」を推奨
実は最近、確認検査機関や適判審査機関側でも「省エネ計算は専門業者に依頼したほうがスムーズです」と明言するケースが増えています。
なぜなら、専門会社の計算書は
- 書式や根拠資料が整っている
- 法改正への対応も早い
- 再提出が少なく、審査が進めやすい
といった理由から、審査側にとってもメリットがあるためです。
設計に集中できる環境を作る
省エネ計算を専門会社に委託すれば、建築士は本来の設計やクライアント対応に集中できるようになります。
設計品質を保ちつつ、スムーズな申請を実現するための選択肢として、アウトソーシングは非常に効果的です。
アウトソーシングのメリット・デメリット
省エネ計算のアウトソーシングには多くのメリットがありますが、外部委託ならではの注意点もあります。
ここでは、建築士が知っておくべき外注の「良い点」と「気をつけたい点」を整理しておきましょう。
アウトソーシングのメリット
1. 業務の時短・負担軽減
省エネ計算にかかる時間を大幅に削減できるため、本来の設計業務や顧客対応に集中できます。
とくに忙しい時期や人手が足りない時に有効です。
2. 最新の法改正や計算方式に対応できる
専門会社は常に最新の建築物省エネ法や評価ツールに対応しているため、安心して任せられます。
法改正のたびに自分で調べて対応する負担も減ります。
3. 審査対応力が高く、申請がスムーズに進む
省エネ適判や確認申請に慣れているため、不備の少ない書類作成が可能。再提出のリスクを最小限にできます。
4. 難易度の高い案件でも対応可能
事務所ビル・工場・商業施設など、住宅以外の非住宅案件にも対応可能な業者も多く、幅広い依頼ができます。
5.省エネ基準クリア検討もスムーズ
多彩なバリエーションの建物を計算し多くの計算実績や経験をノウハウとして持っているため、計算をクリアさせるためのアイデアを豊富に持ち合わせています。
アウトソーシングのデメリット(注意点)
1. 費用が発生する
当然ながら、社内でやるよりもコストがかかるという点は避けられません。
ただし、その分の「時間と安心」を買っていると考えるとコストパフォーマンスは高いです。
2. 設計変更時の再対応が必要になることも
計算後に設計内容が変更されると、再計算や再提出が必要になるため、省エネ計算会社との連携とスケジュール管理が重要です。
3. 業者選びによって対応の質に差がある
すべての専門会社が同じレベルではないため、選定は慎重に行う必要があります(次項で詳しく解説します)。
ポイント💡
アウトソーシングは「楽をする手段」ではなく、確実性と効率性を高める戦略的手段です。
省エネ計算の費用と納期の相場
省エネ計算を外注する際にもっとも気になるのが「費用はいくらかかるのか?」「納期はどれくらい?」という点ではないでしょうか。
ここでは、非住宅建築物を中心に、よくある料金体系と納品までの期間の目安を紹介します。
費用の相場(非住宅建築物)
非住宅(事務所・店舗・倉庫・工場など)では、用途・規模・複雑さによって価格が大きく異なりますが、以下が一つの目安です。
| 用途・規模 | 参考価格(税別) |
|---|---|
| 倉庫・工場(単純な構造) | 30,000円〜 |
| 小規模事務所・店舗(〜300㎡) | 50,000〜80,000円程度 |
| 中〜大規模(500㎡〜数千㎡) | 100,000円〜200,000円以上 |
| 特急対応(3営業日以内) | 別途 +30,000〜50,000円程度 |
※複雑な設備計画や混在用途、断熱補強が必要な場合は追加費用が発生する場合があります。
省エネ計算会社による金額算出方法の違い
省エネ計算会社によって、見積もりの方法が異なります。
面積に対する単価で金額を算出している会社もあれば、どれくらい作業に時間がかかるかによって見積もりを出している会社があります。
一概にどちらが安くなるというのは言い難いですが、長期的なお付き合いを検討されている場合には信頼性や安心感にスピードややり取りのしやすさなど総合的に判断されることをお勧めします。
納期の目安
- 通常納期:5〜15営業日(繁忙期は1ヶ月以上かかることもある)
- 簡易案件・急ぎ対応:3営業日以内(特急料金あり)
- 設計初期からの相談なら、スケジュール調整がしやすく、納品の精度も高くなる傾向にあります。
割引制度や複数案件依頼での交渉も可能
省エネ計算専門会社によっては、
- 初回20%オフのキャンペーン
- 複数棟同時依頼によるボリュームディスカウント
- CASBEEやBELSとのセット割引
などの制度があることも。
費用面での不安がある場合は、見積もり時点での相談がポイントです。
ポイント💡
価格だけでなく、納期・対応力・質問への丁寧さなども含めて判断するのが、失敗しない依頼のコツです。
専門会社を選ぶときのチェックポイント
省エネ計算を依頼する専門会社は数多くありますが、どこに依頼しても同じとは限りません。
大切なのは、自分たちの業務や案件に合ったパートナーを選ぶこと。
ここでは、選定時にチェックしておきたいポイントを紹介します。
1. 対応可能な用途・建物種別
まずは、自分の案件(住宅?非住宅?工場?)に対応しているかを確認しましょう。
特に非住宅(事務所・店舗・工場など)に慣れているかどうかは大きなポイントです。
2. 建築物省エネ法や自治体制度への理解
省エネ計算は、国の制度だけでなく、自治体ごとに異なる基準や書式対応が必要な場合があります。
横浜市や名古屋市など、地方独自の届出制度にも詳しい会社なら安心です。
3. 設計変更や修正への柔軟な対応
設計内容が途中で変更になった場合、再計算や再提出が必要になります。
その際、追加料金の有無・納期対応の柔軟さを事前に確認しておきましょう。
4. コミュニケーションと相談体制
相談や質問にスピーディーに丁寧に答えてくれるかどうかも重要なポイントです。
「専門用語ばかりでわかりづらい」「こちらの要望が伝わりにくい」といったやりとりでは、余計なストレスや手戻りが発生します。
5. 納期・価格だけで選ばない
「安いから」「早いから」といった理由だけで依頼先を決めるのは要注意です。
審査対応や品質の差が結果的に再提出・遅延・信頼損失につながることも。
ポイント💡
「この会社なら安心して任せられる」と思えるパートナーを選ぶことが、長期的な業務効率化と信頼関係の構築につながります。
依頼前に準備しておくべき書類・情報
省エネ計算をスムーズに進めてもらうには、依頼時点で必要な情報を揃えておくことがカギになります。
ここでは、アウトソーシング時に用意しておくべき代表的な書類と情報をまとめておきます。
必ず必要な図面・資料
| 書類名 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 配置図 | 建物の方位・敷地形状を確認するために必要 |
| 平面図 | 各階の間取り・部屋用途・窓の配置を確認できるもの |
| 立面図・断面図 | 建物の高さ・断熱範囲・開口部の把握に使用 |
| 窓・建具表 | サッシの種類・ガラス構成などの情報 |
| 電気・設備関連の資料 | どこにどんな機器がついているかの情報と機器の仕様書 |
その他の必要情報
- 断熱仕様の一覧(外壁・屋根・床・開口部などの性能値)
- 設備仕様(空調、照明、給湯、換気の内容と方式)
- 対象建物の用途・延べ面積・階数
- 建築地の地域区分(1~8地域)
- BELSやCASBEEなど、併用予定の制度があるかどうか
初回相談で伝えておくと良いこと
- 計算の目的(確認申請・適判・性能評価など)
- 設計の進行状況(基本設計中/実施設計中 など)
- 納期の希望と予定している確認申請日
- 計算に使いたい評価方法(モデル建物法 or 標準入力法 など)
ポイント💡
「何が必要かわからない」場合でも、まずは設計図面一式と計画概要を共有するだけでもOK。
専門会社がヒアリングしながら不足情報を整理してくれる場合も多いです。
まとめ
省エネ計算は、建築士にとって避けて通れない業務のひとつですが、年々その内容は複雑になり、設計業務と並行して対応するのは大きな負担となっています。
こうした背景から、省エネ計算を専門会社にアウトソーシングする動きが広がっており、審査機関からも推奨されるケースが増えています。
時間・労力を削減できるだけでなく、審査対応の精度やスピードも向上するなど、多くのメリットがあります。
ただし、依頼先によって対応力や品質には差があるため、対応範囲・実績・柔軟性・相談体制などをよく確認したうえで、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。
「設計に集中したい」「申請を確実に通したい」と感じたら、
まずは実績豊富な省エネ計算専門会社へご相談ください。
私たちは、非住宅案件を中心に、設計段階からのサポートも行っています。
お気軽にこちらからご相談いただけます👇
お問い合わせはこちら